タンデム自転車はパラリンピックの自転車競技にもなり、東京でも2023年7月から公道走行が解禁となりました。
しかし、一般的な自転車とは交通ルールも少し違うため注意が必要です。
今回はタンデム自転車の特徴と交通ルール、メリットデメリットを調査しました。
(アイキャッチ画像出典元:https://www.yomiuri.co.jp/national/20230628-OYT1T50090/)
タンデム自転車の特徴

(画像出典元:http://blog.livedoor.jp/mk7054-vol2/archives/54623223.html)
タンデム自転車とは、複数のサドルとペダルを装備し、複数人が前後に並んで乗り同時に駆動することができる自転車です。
デンマーク人のミカエル・ペデルセンが発明し1893年に特許を取得したという記録が残されています。
後部座席はハンドルはあるものの持ち手としての役割のみで操縦はできず自転車を漕ぐだけになり、前の座席に座っている人が操縦することになります。
タンデム(tandem)は、二つのものが連結されている状態や、協力して働くことを意味しており、オートバイの二人乗りや小型航空機の座席配置を指す際も使われます。
通常2人乗りですが、3人、4人、5人乗りのものもあります。
以前は自転車専用道路等を除く一般公道でのタンデムサイクリングが禁止されていましたが、1978年に長野県が公道走行を解禁し、その後徐々に広がり、2023年7月に東京が解禁し、全国で公道走行可能となりました。
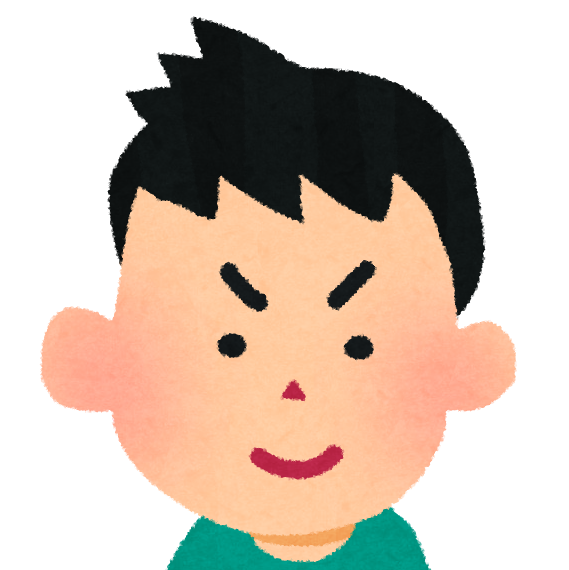
1893年に発明されたんだね。
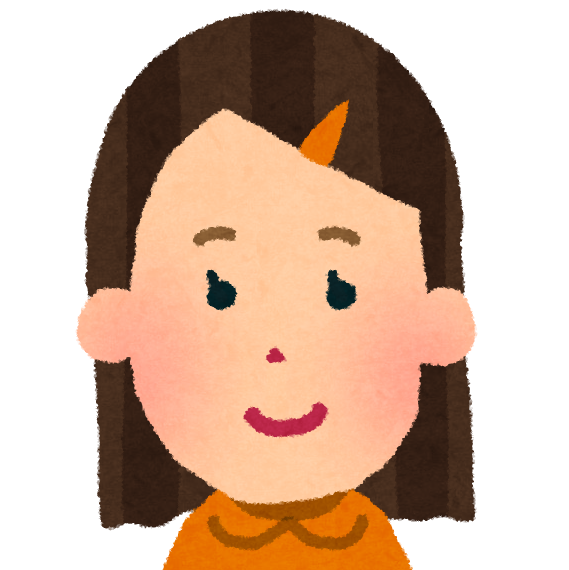
全国で公道走行が可能なのね。
タンデム自転車の交通ルール

(画像出典元:https://jitemani.com/sign-except-bicycle/)
道路交通法では、乗車装置(幼児用を除く)が一つ、全長190cmまでのものが「普通自転車」と定めており、標識などで単に「自転車」とある場合は「普通自転車」を指します。
タンデム自転車は「普通自転車」とは異なるため、走行には注意が必要です。
- 歩道は通行不可
- 自転車及び歩行者専用の交通規制の通行不可
- 「自転車を除く」は対象外
- 「軽車両を除く」は対象
歩道は通行不可
普通自転車は、原則車道を走行し、例外的に歩道を通行することが可能ですが、タンデム自転車の場合は、例外なく車道のみの走行となります。
自転車及び歩行者専用の交通規制の通行不可
タンデム自転車は普通自転車に該当しないため、自転車及び歩行者専用の交通規制では、通行することができません。
「自転車を除く」は対象外
車両通行止め・車両進入禁止・一方通行などの標識に付帯している「自転車を除く」では、タンデム自転車は対象となりません。
「軽車両を除く」は対象
軽車両には、全ての自転車を含むため、「軽車両を除く」とある場合はタンデム自転車はその規制除外の対象となります。

普通自転車と交通ルールが少し違うので注意しなくちゃね。
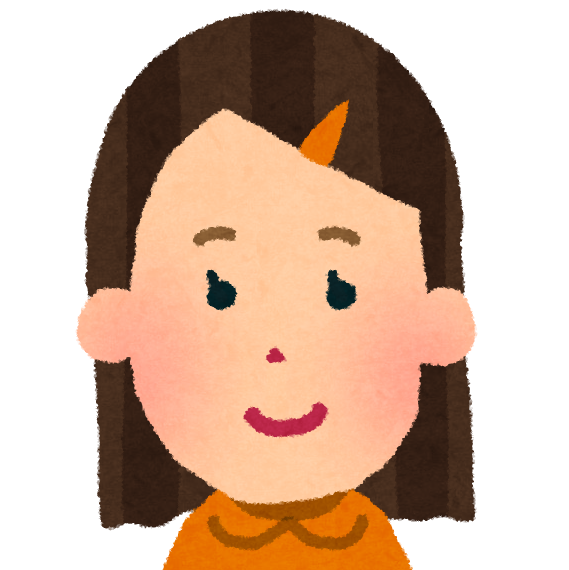
歩道は自転車から降りて押して歩けば通行できるわ。
タンデム自転車のメリットデメリット

(画像出典元:https://withnews.jp/article/f0181230000qq000000000000000G00110101qq000018561A)
メリット
- 視覚障害を持つ人でも一緒に走行でき、行動範囲を広げられる
- 会話しながら協力して走れる
- 出力が2倍で空気抵抗はあまり変わらないためスピードが出る
デメリット
- スピードが出やすい
- 車体が長いため小回りがきかず、バランスを取りずらい
- 持ち運びが大変
- 交通ルールが普通自転車と異なる
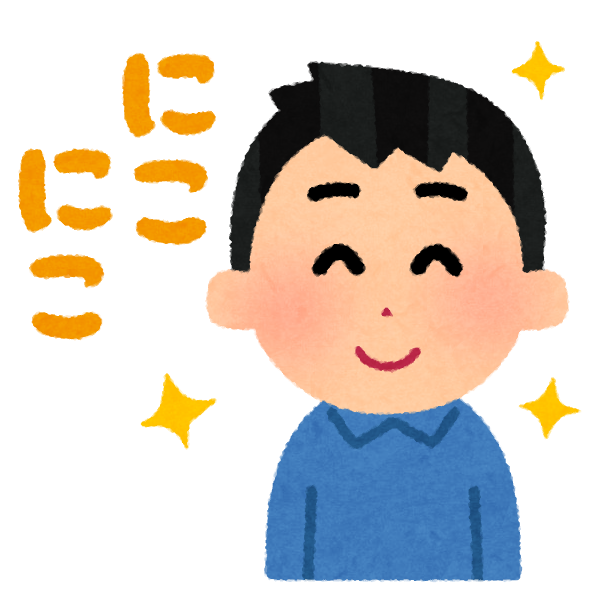
視覚障害を持つ方も乗れるのはいいことだね。

スピードの出し過ぎには注意が必要ね。
まとめ
タンデム自転車は、視覚障害のある方でも風を切る爽快感が味わえるのがとても素晴らしいですね。
交通ルールを正しく理解し、安心・安全に楽しく利用しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。






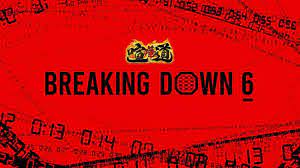


コメント